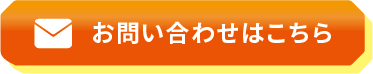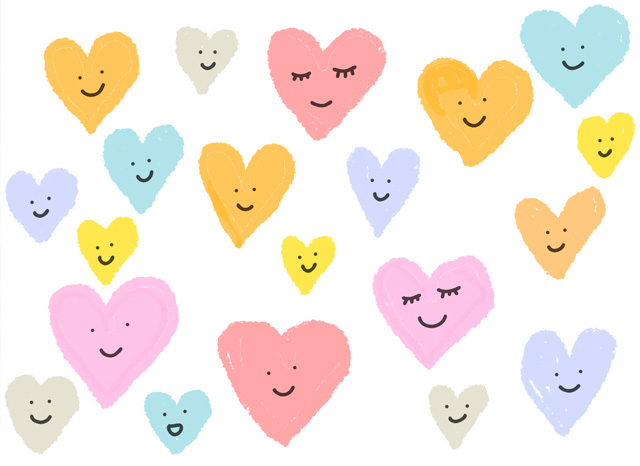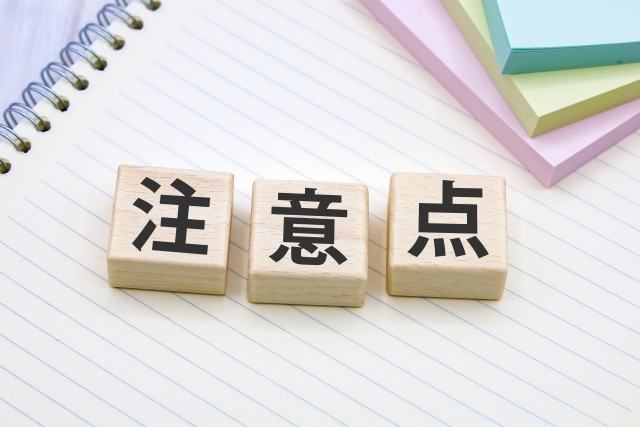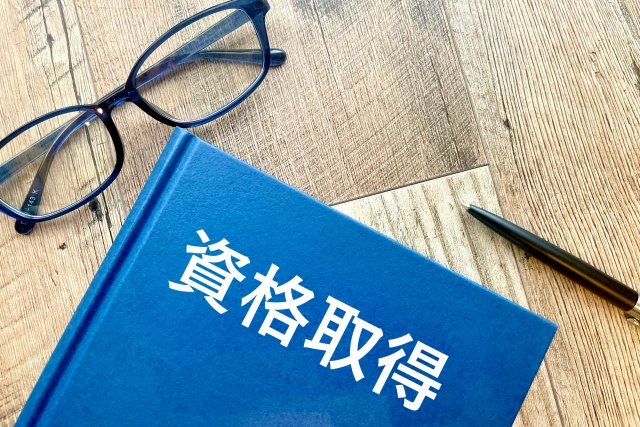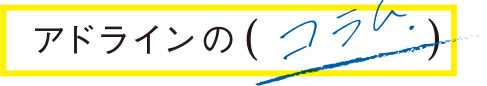
-
ホームページ制作2024.02.21

「自分でホームページを作成したい!」
「ホームページはスマートフォンで簡単に作成・更新できる?」
「スマートフォンでホームページを作成する、おすすめの方法を知りたい」ホームページは今やビジネスに欠かせないツールのひとつ。日々仕事で忙しく、作成や運営・更新がつい後回しになっている人もおおいのではないでしょうか。場所や時間を問わず、スマートフォンひとつで簡単に制作できると便利ですよね。
この記事では、スマートフォンでホームページを作成する方法について紹介します。作成に役立つアプリやコツなどもあわせて解説するので、ホームページを作成するときに役立ててくださいね。
スマホでホームページ作成するメリット
近年では、スマートフォンがあればホームページを作ることのできるアプリが増えてきており、専門的な知識がなくても気軽かつスピーディーにホームページが作成できます。既存のテンプレートを選択して、必要事項を記入すれば、大まかなホームページが完成するのです。
まずは、スマートフォンでホームページを作成するメリットについて紹介します。
誰でも手軽に作成!
本来、ホームページ作成にはHTMLやCSS、デザインなど専門的な知識や経験が必要です。パソコンを普段使わない人や、専門的な知識のない人にとってはハードルが高いと感じてしまうかもしれません。
スマートフォンからアプリを使えば、そのような知識が不要なため誰でも手軽に作成できます。アプリのダウンロードやテンプレートの選択、必要事項の記入で作成完了です。
移動中や仕事の隙間時間など、場所や時間を問わず作成できるのも魅力といえます。忙しい人にとっては重宝するでしょう。
更新も簡単!
ホームページは作成だけでなく、その後の更新作業も必要不可欠です。スマートフォンのアプリを使えば、情報の修正やブログ記事の更新などもスマートフォンから行うことができます。
無料アプリ・ツールあり
ホームページ作成にはさまざまなアプリが使えますが、中には無料で利用できるものもあります。気軽に作成できるため、まずはお試しでホームページを作ってみたい人にぴったりです。
ただし、作成のサポート対応やオプションなど、一部のサービスが有料となっている場合もあります。無料で利用できる範囲をあらかじめ確認しておくと安心です。
コスト・時間の削減にも
ホームページのデザインは既存のテンプレートを利用するため、外部のデザイナーとの打ち合わせや依頼する手間、外注費用はかかりません。
ゼロからの作成と比べてコストや時間をかけずに、ホームページが完成します。
スマホでホームページを作成する方法
ここからは、スマートフォンでホームページを作成する方法を紹介します。スマートフォンのアプリやブラウザを使って、気軽にホームページを作成してみましょう。
アプリを使って作成
まずは各サービスの公式サイトにアクセスし、アプリとブラウザどちらで作成できるのかを確認しましょう。
アプリを使って作成する場合は、「App Store」や「Google Play」からアプリをダウンロードする必要があります。ユーザー登録や初期設定を終えてから、テンプレートを選択し、ホームページ内の文章や画像、コンテンツの作成などを行います。
ブラウザ版で作成
サービスによっては、アプリだけでなくブラウザ版でも作成・更新可能です。作成の流れはアプリを使う場合とほとんど変わらないものの、アプリのダウンロードは必要ありません。アプリの不具合などに備えて、アプリとブラウザ版の両方が使えるサービスを選ぶのも賢い方法です。
スマホでホームページ作成できるおすすめアプリ・ブラウザを紹介!
ここからは、スマートフォンからアプリとブラウザ版の』追加両方でホームページを作成できるサービスを紹介します。
Jimdo
「Jimdo(ジンドゥー)」は世界中で活用されているホームページ作成サービスです。スマートフォンで、感覚的かつスムーズに作成できます。初心者なら、ナビに従って選択していくだけでホームページ作成できる、独自のシステム「ジンドゥーAIビルダー」を使うのがおすすめです。
分からないことがあれば、日本人スタッフによるサポートが受けられるのも嬉しいポイントです。作成や基本のプランは無料で利用できますが、優先サポート対応や広告の非表示などを含む有料プランも用意されています。
Wix
「Wix」は無料でホームページ作成・管理が可能なサービスです。900種類以上のテンプレートから好みのデザインを選ぶことができます。
画像や文章を感覚的に自由に配置でき、スマートフォンのアプリやブラウザ版で感覚的に調整できるのは、初心者にとっては安心ポイント。サイト最適化には欠かせないSEO機能や、セキュリティ機能の高さに定評があります。ネット予約システムやネットショップとしても活用可能です。
共同編集ユーザーやデータ容量を増やしたり、便利な機能も追加したりできる有料のプレミアムプランも。用途にあわせて活用できるサービスです。
foriio
「foriio」はクリエイターのポートフォリオ作成に特化したサービスです。デザインや写真、記事などをひとまとめにし、自分のポートフォリオとしてページ上で見やすく追加・整理できます。感覚的にサクサクと操作できるため、忙しくてポートフォリオの管理まで手が回らない人におすすめです。アプリとブラウザ両方から作成・管理できます。
有料プランでは、パスワード機能や画像の透かし機能、ロゴ非表示など便利な機能が充実しています。ポートフォリオとしてホームページ作成を検討している人は、こちらも検討してみましょう。
スマホでホームページを作るデメリット
スマートフォンのアプリやブラウザ版でホームページを作成するのは、とても簡単かつスムーズな一方、デメリットもあります。
まず、作成には既存のテンプレートを使うため、完全なオリジナルのホームページを作るには向いていません。無料のサービスの場合、インターネット広告の表示が消せなかったり、使うことのできる機能に制限があったりして、不便さを感じることもあるでしょう。
さらに、サービス提供の終了により、ホームページが強制的に閉鎖されたり管理ができなくなったりするケースも考えられます。これらのデメリットを把握したうえで、対策を考えるのが賢い方法です。
まとめ|ホームページ作成のことならアドラインプラスにおまかせ!
スマートフォンのアプリで作成するホームページは、専門的な知識が必要なく手軽です。すぐにホームページを完成させたい場合や、お試しで作成してみたい場合にはぜひ活用してみましょう。文章や画像、コンテンツ内容にこだわってホームページを充実させてみてくださいね。
テンプレートでは作成できないような、オリジナリティのあるホームページを作成するなら、プロであるホームページ制作会社に依頼するのがおすすめです。
株式会社アドラインプラスは、ホームページ作成の実績が豊富なデザイン会社です。あなたのイメージを丁寧に聞き取り、ニーズにあったオリジナルのホームページをご提案します。無料相談も行っているので、まずはお気軽にお問い合わせください。
-
動画制作2024.01.23
「試しにドローンを飛ばしてみたい!でもスペースがない…」
「身近にドローンを飛ばせる場所はある?」近年、急速に普及しつつあるドローン。個人的にドローンを持っていて、さまざまな場所で空撮を楽しむ人も増えてきています。
屋外で、警備や測量などの業務目的で飛ばすには免許取得や警察への申請が必要な場合があるものの、許可されている場所で個人的にドローンを使う場合には必要ありません。※法改正により、令和4年6月20日以降、機体登録を行っていないドローン(100g未満のものは除く)は、屋外で飛行できないためご注意ください
空撮や練習目的でドローンを飛ばしてみたいけれど、警察への申請や免許取得は大きなハードルとなりやすいもの。
申請や免許が必要ない、ドローンを飛ばせる場所が知りたい人も多いのではないでしょうか?この記事では、愛知県内でドローンを飛ばせるスポットを紹介します。
警察への申請や免許取得をしていなくても、管理者への事前予約で利用できるスポットばかりですので、参考にしてくださいね。ドローンパーク名古屋(名古屋市)
名古屋市中川区の「ドローンパーク名古屋」は、名古屋市内で唯一の屋外ドローン練習飛行場です。東側に新川が隣接し、西側には名古屋第二環状自動車道や戸田川緑地が近接する立地です。縦は最大300m、横は最大200mと空撮に十分な広さが確保されています。
練習から空撮まで、幅広い用途で使える施設です。屋外でドローンを飛ばすのに必要な、関係官庁や警察などとの調整は施設側で行われているのも安心できるポイントといえます。
ドローンの貸し出しも行われているので、まずはドローンを操作してみたいという人にもぴったり。
なお、バッテリーの充電設備は設置されていません。そのため、バッテリーを複数準備しておくと良いでしょう。利用にはメールでの事前予約が必要です。
・住所:名古屋市中川区江松2丁目
・使用可能時間:9:00~17:00、夏季(7月~9月)9:00~18:00
・料金:3時間6,000円~
・公式サイトURL:http://npo-ndsa.org/event.htmlFREIHEIT(名古屋市)
名古屋市中川区でドローンビジネスを展開する会社「FREIHEIT」内にも、屋内ドローン練習場が設置されています。
天候や時間に関係なく、安全な環境でドローンを飛ばせるのが屋内練習場の魅力です。練習場内には人工芝が敷かれ、天井も高くなっています。
大人だけでなく子どもの利用が多いのも特徴です。子どもがドローン練習場で操作する様子を、すぐそばにあるカウンター席から見学することができます。トイドローンのレンタルも可能です。
ドローンの練習はもちろんのこと、それ以外での活用も相談できるのが嬉しいポイントです。サークルのイベントやフォトスペースなどに利用されることもあります。
・住所:名古屋市中川区中須町194
・予約可能時間:9:00~18:00(最長20時まで)
・料金:1時間2,000円~
・公式サイトURL:https://freiheit-drone.com/#spaceTAKIDENKI JAPAN(江南市)
「TAKIDENKI JAPAN」は、ショッピングセンターの一画にあるマイクロドローンサーキットです。
限られたスペースを活用し、手作りのサーキットを設置しています。月曜日を除く平日は、小中学生の利用料が無料。子どもの利用が多い施設です。高校生以上でも1時間500円と格安なため、ドローン操作の練習をしたい人に向いています。
また、不定期でイベントが開催されることも。最新のイベントは、公式サイトのカレンダーやFacebookで確認しましょう。
・住所:江南市前飛保町河原33 江南ショッピングタウンピナ1F
・使用可能時間:10:00~18:00
・料金:1時間500円
・公式サイトURL:http://www.takidenki.co.jp/takidenkijapan/index.htmlポラリスドローン練習場(日進市)
日進市の「ポラリスドローン練習場」は、ドローン練習スクール内にある屋内練習場です。
屋内ながら天井は高めで、天候を気にすることなく操作の練習ができます。駐車場は10台分が完備され、名古屋市内からアクセスしやすい立地も魅力です。
練習場は貸切利用が可能です。他に利用者がいないため、ドローン同士の衝突などの心配がなく集中して利用することができます。
また、スクール内の練習場のため、個人練習だけでなくレッスン利用ができるのが特徴です。スタッフのマンツーマン指導のもと、自分のレベルやペースにあわせて練習できます。操作に関しての疑問点の解消や、さらに操作スキルを向上させたいときに役立つでしょう。
なお、スクールの会員でない場合、入会金5,000円が別途かかります。
・住所:日進市浅田町平子4番地の301
・使用可能時間:
・料金:1時間5,000円~
・公式サイトURL:https://www.polaris-export.com/観光農園花ひろば(南知多町)
南知多町の「観光農園花ひろば」は、ドローンの空撮に挑戦してみたい人におすすめのスポットです。
観光客向けにいちご狩りやメロン狩りを行うほか、季節の花々が咲き誇ります。映画やテレビ番組の撮影に使われることも。色とりどりの花々が咲き誇る農園は、空撮にぴったりです。
料金や使用可能時間は、予約の際に電話確認するのがマスト。ドローンが飛行可能なエリアも限られているため、あわせて確認しておきましょう。
・住所:知多郡南知多町豊丘高見台48
・使用可能時間:日によって異なる
・料金:有料
・公式サイトURL:http://www.hana-hiroba.net/2017/07/愛知ドローンスクール(岡崎百々西校、西尾幸田校、岡崎フライトベース飛行場)
愛知県岡崎市の「愛知ドローンスクール」は民間ライセンス&国家資格対応ドローンスクールです。
スクール設備は常設なので屋内練習場・屋外飛行場はドローンを持っているどなたでも利用OK。広さ1000坪!ネット内(21m×15m×7m)の屋外ですが、屋内扱いエリアもあり!登録前機体や実験用機体・初飛行で不安な方のお悩みも解消! 屋内練習場は毎週金曜よる6時~10時まで1000円でトイドローン・マイクロドローン飛ばし放題練習会【フライデードローンナイト】を開催しています。 身近にドローンを楽しんでもらいたい!練習する場所が欲しい!ニーズにお応えします!
・住所:愛知ドローン岡崎フライトベース野外飛行場 愛知県岡崎市滝町大皿田4-1
愛知ドローン岡崎百々西校 フライデードローンナイト(毎週金曜6時~)愛知県岡崎市百々西町3-2
・使用可能時間:日によって異なる
・料金:1日利用は1500円、1カ月飛ばし放題3000円、修了審査飛行練習は1時間5000円
・公式サイトURL:http://aichidrone.net愛知県でドローンを飛ばせないスポットは?
愛知県警では法律に基づき、重要施設及びその周囲おおむね300メートルの周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行を禁止しています。この小型無人機にはドローンも含まれています。ドローンを飛ばす前に、空港や自衛隊基地などの重要施設が周辺にないか確認しておくとよいでしょう。
同じ愛知県内でも自治体によっては、法律に関係なくドローンの使用を認めていないスポットがあることも。例えば、名古屋市内の公園では原則として、ドローンの使用が認められていません。航空法上で無人航空機の定義に該当しないドローンも同様に認められていないため注意しましょう。
まとめ|愛知県でドローン空撮を依頼するなら
愛知県内で、警察への申請や免許取得が必要のないドローンスポットを紹介しました。操作の練習から本格的な空撮まで、必要に応じて活用してくださいね。
屋外でドローンを使った空撮を検討しているなら、プロの手を借りてみてはいかがでしょうか。
名古屋市に本社を置く株式会社アドラインプラスでは、協力会社の力をかりてドローンによる空撮を行っています。空撮だけでなく動画の編集作業まで一貫して対応可能です。愛知県内で空撮を検討している場合はぜひご相談ください。
-
デザイン制作2024.01.23
「自分でデザインをするのは難しいので、誰かにお願いしたい」
「デザインはどこにお願いすればいいの?」
「デザインをお願いするときに必要なのはどんなこと?」新規サービスのチラシや展示会用の会社パンフレット、製品カタログや採用のためのホームページなど…
デザインは自分で制作することも可能ですが、納得できるデザインに仕上がらなかったり、必要なツールやソフトが操作できなかったりして、デザイナーへの依頼を検討している人も多いのではないでしょうか。これまでにデザインをお願いしたことがなく、誰にお願いすればよいのかやお願いするときに必要なものが分からないと不安ですよね。
この記事では、デザインをお願いする方法や注意点、必要なものを解説していきます。
デザインをお願いする前に検討すべきこと
まず、デザインをお願いする前に検討しておきたいことがいくつかあるので紹介します。「とにかくお願いしてみよう!」と何も決まっていないままでお願いするよりも、スムーズにやりとりが進むはずです。
誰にお願いするか
デザインを誰にお願いするかを決めましょう。一般的にはプロのデザイナーにお願いするケースが多いです。
● これまでにデザインをお願いしたことがあるデザイナー
● デザイナーを抱えるデザイン会社
● 特定の会社に属さない、フリーのデザイナーなどの選択肢があります。会社やデザイナーによって得意なデザインの分野や費用、デザインの制作フローが異なります。事前に複数の会社やデザイナーを比較して、実績を見ておくのが良いでしょう。
デザインをお願いする理由
デザインが必要になった理由は明確にしておきましょう。
「新しいサービスを立ち上げることになったので、必要なデザイン一式をお願いしたい」
「イベント開催のため、告知のチラシのデザインをお願いしたい」などとお願いする理由が明確になっていれば、デザイナーとの打ち合わせやデザイン制作がスムーズに進みます。経験のあるデザイナーであれば、提案をもらうことも可能です。
完成までのスケジュール
デザインをお願いしてから完成するまで、
● 打ち合わせ
● デザイン制作
● 構成提出、確認、修正(こちらを費用に応じて数回繰り返します)
● データ納品。もしくは印刷依頼など、たくさんの工程があります。場合によっては打ち合わせや修正が複数回発生することもあります。デザインの提案の数によっても、費用が変わります。デザインが完成するまでの工程が無事終えられるようにしましょう。
あまりにも納期までの時間が短い場合、デザイン会社やデザイナー側が依頼を受けられなかったり、見積もりに割増料金が発生したりすることもあります。納期までに確実にデザインを完成させられるよう、余裕をもたせて依頼するタイミングを考えましょう。
デザインにかかる予算
デザインをお願いする際には予算を明確にしておきましょう。予算が明確になっていたほうが、依頼を進めやすくなります。
デザインをお願いするときに必要なもの
デザインを依頼する際には、依頼者側が用意しておくべきものもあります。ここからは、デザインをお願いするときに必要なものを紹介します。あらかじめ手元にそろえておいて、お願いするときにあわてないようにしましょう。
テキスト・画像データ
デザイン会社やデザイナー側で用意するのが難しい、テキストや画像・動画のデータは必ず用意しておきましょう。例えば会社・お店の様子を撮影した画像や、デザインの中に盛り込む必要のある情報など、依頼者側でしか手配できないものです。画像や動画の場合はできるだけ元データを渡しましょう。あらかじめこのようなデータを共有しておくと、やりとりもスムーズに進むはずです。ただし、完成度を高める場合や急ぎの場合などは、プロのコピーライターやカメラマンに頼むなど、プロの力を借りる方が納期も短くでき、完成度も上がります。
完成イメージ
打ち合わせやメールのやり取りだけでなく、手書きでもいいので、ご自身の考えているイメージを渡すのもおすすめです。手書きでまとめた簡単なイメージでかまいません。デザイナー側もデザインの完成形がイメージしやすくなり、制作費用の削減ができる場合もあります。
難しい場合は、参考として好きなデザインサンプルを共有するのも良いでしょう。その場合は、参考にした既存のデザインと全く同じにならないように固執しない必要があります。
見積もり書の説明をもらう
どこまでを依頼し、どこまで自分で行うのかなどを考えて、見積もり内容をきちんと確認しましょう。デザイン案の数、校正回数など、手がかかればかかるほど見積金額は上がりますが、選択肢も広がり完成度は高まります。
費用対効果を考えて、どこまで依頼すべきかを絞りこみます。
また、必ず見積もりは説明を受けましょう。きちんと説明を受けていないと、「言った言わない」の争いが起こることも考えられます。
デザインをお願いしたときの注意点
デザイナーの制作がスムーズに進むよう、依頼者側にも注意しておきたいことがあります。ここからは、デザインをお願いしたいときの注意点について解説していきます。
依頼後の大幅な内容変更は、ほどんどの場合が追加料金が発生します
デザインの制作を開始した後にも、小さな変更点の発生はあるでしょう。しかし、依頼内容を途中で大幅に変更するようなことは避けるべきです。
例えばデザインのターゲットの変更。性別や年代などのターゲットを変更すると、デザインそのものの作り直しが必要になるケースもあります。
依頼内容の変更により大幅な修正が必要になると、スケジュールに影響が出るだけでなく、追加料金が発生する場合もあります。依頼内容の大幅な変更がないよう、依頼前に内容をしっかりと確定させたうえで、打ち合わせに臨みましょう。
修正依頼は明確に
デザインの修正をお願いする場合は、修正内容を明確にしましょう。修正が必要な理由とともに、どの部分をどのように修正するかを明確に伝えましょう。既存のデザインや画像をもとに伝えるのも分かりやすくておすすめです。あいまいな内容で修正回数が増えると無駄に追加料金が発生します。訂正意図がきちんと伝われば、デザイナーによる提案も引き出せます。
丸投げは別途費用がかかります
「とりあえずお願いしたい」とすべてお任せでお願いしようとする、いわゆる丸投げは別途ディレクション費用(提案、調査費用など)がかかります。デザインの用途やターゲット、完成イメージがないままデザインを進めると、作り直しや大幅な修正が必要になるケースがあるためです。丸投げしたい場合は、ディレクターを入れるのが一般的です。
費用を抑えたい場合は、丸投げではなく、お互いが共通の完成イメージを持った状態でデザイン制作をスタートできるようにしましょう。
まとめ:デザインのことならアドラインプラスにおまかせ!
デザイナーにデザインをお願いしたいときの注意点や方法を紹介しました。自分でデザインを考えるのが難しいときは、ディレクターがいるデザイン会社やプロのデザイナーへの依頼を検討してみてくださいね。
株式会社アドラインプラスは、「デザインをお願いしたい」というニーズを叶えるデザイン会社です。ディレションができる経験豊富なデザイナーがお客様の要望や課題を丁寧にヒアリングし、イメージとぴったりのデザインを制作させていただきます。無料相談も行っているので、まずはお気軽にお問い合わせください。
-
コミュニティ運営2023.10.31
「コミュニティ運営って何?どうすれば良いの?」
「ビジネスにも活用できるの?」
「コミュニティ運営をしてみたい」企業のファンの獲得や情報発信などにも使われる機会が増えている、コミュニティ運営。趣味やビジネスの場面で、コミュニティ運営に挑戦しようと思っている人も多いのではないでしょうか。コミュニティ運営の経験がないと、まず何から取り掛かれば良いのか不安になりますよね。
この記事では、コミュニティ運営について解説します。ビジネスにも活用できるコツやポイントなどもあわせて紹介するので、コミュニティ運営に役立ててくださいね。
コミュニティ運営とは
コミュニティとは、価値観や目的など共通点の多い人々が集まる場所のこと。単にコミュニティを作るだけでなく、情報や意見を交換したり、イベントを開催したりして運営することが必要です。芸能人やスポーツ選手を応援するコミュニティや企業が運営するコミュニティまで、さまざまな目的のコミュニティが存在しています。
ここからは、コミュニティを運営するメリットを紹介します。
ビジネス面でも活用できる!
コミュニティ運営はビジネス面でも活用できます。特に企業によるコミュニティは、マーケティング戦略の一環として運営するケースが多いのが特徴です。
さらに、WebやテレビCMでの広報活動と同様に、最新情報を発信したりお得なクーポンを提供したりして、ファンの獲得も実現できます。企業のブランディングにも役立つでしょう。コミュニティ運営を成功させ、ビジネスの機会につなげたいところです。
ニーズを把握することもできる
コミュニティを運営すると、ユーザーの声をダイレクトに聞くことができます。ユーザーの声は、マーケティング戦略に必要なニーズの把握や改善にも有効的です。
企業の場合、サービスや商品を購入してもらった後もユーザーとの接点を持つことができ、さまざまな場面で活かせます。接点があると、ニーズの把握のためのアンケートも実施しやすくなるはずです。
知名度アップにも
まだ知名度の低い企業やサービスを広めるために、コミュニティ運営が活用されることもあります。コミュニティ運営がうまくいけば、コミュニティ外にもその盛り上がりが広がり、知名度にアップにつながるでしょう。
個性的なコミュニティの運営をきっかけに、メディアで話題となりファンを増やしたケースも。広報活動としても活用したいところです。
コミュニティ運営に必要なこと
コミュニティ運営を始める前に、コミュニティの作り方や運営方法を知っておきましょう。ここからは、コミュニティ運営に必要なことを解説します。
目的をはっきりとさせる
まずは、コミュニティ運営をする目的をはっきりとさせておきましょう。
コミュニティ運営の目的は、ユーザー同士の情報共有からニーズの把握、知名度アップまでさまざまです。目的として、どのようなメリットを得たいのかを明確にしておくのがマストです。
運営の形式を決める
目的が明確になれば、どのような運営形式をとるか決めましょう。直接ユーザーの顔を見て声を聴きたい場合はオフラインで、場所を問わずさまざまなファンを獲得したい場合はオンラインで、と目的にあわせた形式を考えるのが大切です。
オンラインがメインでも、イベント内容によってはオフラインで開催も取り入れ、臨機応変に運営しているコミュニティもあります。
ユーザーの集客・管理
コミュニティには、参加するユーザーが必要不可欠です。ユーザーを増やすために集客を行いましょう。集客には公式サイトの開設やSNSでの発信、キャンペーンの実施などさまざまな方法があります。
ユーザーの集客だけでなく、ユーザーが離れていかないよう管理もしっかり行いましょう。コミュニティを継続させるためにも大切なことです。コミュニティ内のコンテンツや情報発信、イベント開催などを充実させ「コミュニティに参加してよかった」と思ってもらえるようにしましょう。
管理に割ける時間や費用が限られている場合、まずは少人数のユーザーに絞って運営をスタートするのもひとつの方法です。
コミュニティを盛り上げる
運営を成功させるためには、コミュニティの活性化がカギをにぎります。ユーザーの集客や離脱防止にも効果的です。
コミュニティを盛り上げるには、ユーザーにとって需要のあるイベントやキャンペーン、情報発信などさまざまな方法があります。コミュニティに参加するユーザー限定の特典やメリットを考えるのも良いでしょう。
また、ユーザー同士で交流できる仕組みを作るのもひとつの方法です。ユーザー同士の活発な交流が、コミュニティ全体の盛り上がりにつながるでしょう。
長期的に取り組む
コミュニティ運営を成功させるには、長期的な戦略を持って取り組むことが必要です。運営を始めた当初はユーザーがなかなか増えず、思うように盛り上がらないこともあります。そのような状況で、結果を出すことを優先すると、かえってユーザーが離れていく可能性も。
目的を果たすためにも、焦らず長期的な戦略を練ってコミュニティを運営しましょう。しっかりと時間を確保して運営を行うか、限られた時間の中でも運営できるような体制を整えておく必要があります。
初心者は注意!よくある失敗
次に、コミュニティ運営でよくみられる失敗を紹介します。失敗パターンを把握し、同じ失敗をしないよう注意しましょう。
運営の時間が確保できない
コミュニティを運営する時間が確保できないケースもよくあります。想定していた以上に時間がかかり、結果としてコミュニティ運営の継続が難しくなる状況が考えられます。
運営に割く時間が十分でないと、コミュニティが活性化せずユーザーが離れていく原因にも。時間がかかることを前提に、コミュニティ運営を行いましょう。
トラブルが起こる
ユーザーとやりとりをする以上、どうしてもトラブルが起こる可能性があります。ユーザー同士の交流機能がある場合は、ユーザー同士のトラブルが起こることもあるかもしれません。
トラブルを未然に防ぐためには、コミュニティ内での金銭のやりとりの有無にかかわらず、さまざまな想定をして規約やルールを考えておきましょう。
短期間で結果を出そうとする
先述のとおり、運営を始めた当初はユーザーがなかなか増えない可能性があります。すぐには成功に結びつかないことを踏まえ、短期間で結果を出そうと焦らないようにしましょう。
まとめ:コミュニティ運営のことならアドラインプラスにおまかせ!
コミュニティ運営には、マーケティングへの活用やファン獲得、認知度アップなどさまざまな効果があります。成功のためには継続的な運営が必要不可欠ですが、うまく活用できればビジネスの場面でも大いに役立つでしょう。コツや失敗パターンを把握し、コミュニティ運営にぜひ挑戦してみてください。
株式会社アドラインプラスでは、コミュニティ運営の一環として、名古屋のデザイン関係者の交流会「十五夜会」を毎月15日に開催しています。デザイン関係のさまざまな職種の人が集まり、参加者同士の交流も活発です。気になる方はぜひ参加してみてください。
-
デザイン制作2023.08.02
「グラフィックデザイナーとはどんな職業?」
「どうやったらなれるの?」
「どのような人が向いているの?」グラフィックデザイナーとは、おもに紙媒体のデザインを制作する仕事のことをいいます。商品パッケージやポスターなど、手がけるデザインはさまざまです。日常生活に欠かせないデザインを手がけるグラフィックデザイナーの仕事に憧れている人も多いのではないでしょうか。グラフィックデザイナーを目指すうえで、自分が向いているかどうかも知っておきたいところ。
この記事では、グラフィックデザイナーの詳しい仕事内容や必要な能力などを解説し、どのような人が向いているのかを紹介していきます。
この記事を読むと、グラフィックデザイナーの仕事のイメージをつかみ、自分が向いているかどうかを知ることもできます。ぜひ読み進めてください。
グラフィックデザイナーとは?
グラフィックデザイナーとは、日常生活で見かける広告や新聞、雑誌や本、商品パッケージなどをデザインする仕事です。紙媒体のほか、ポスターや看板のデザインも含まれます。
グラフィックの言葉の意味は「視覚に訴える表現」、デザインは「設計・図案」です。この言葉からも、視覚に訴えかけるような表現を考える仕事だということがわかります。
おもな勤務場所は広告制作会社や企業の宣伝・広報部、印刷会社やデザイン会社などとなっています。働き方も正社員やアルバイトから、業務委託のフリーランスまでさまざまです。
Webデザイナーとの違い
グラフィックデザイナーとよく似た職業に「Webデザイナー」がありますが、Webデザイナーは紙媒体ではなく、おもにWebサイト(ホームページ)をデザインする仕事です。会社や人によっては、グラフィックとWeb両方の領域でデザインを行っている場合もあります。
紙媒体とWebサイトの違いはあるものの、要望やイメージをデザインとして表現する点では同じです。
グラフィックデザイナーに向いている人は?
グラフィックデザイナーの仕事には、デザインが好きであること以外にもさまざまな能力や適性が求められます。ここでは、グラフィックデザイナーはどんな人に向いているのかを解説します。
視覚に訴えるデザインを制作できる人
グラフィックデザインでは、視覚に訴えかけるようなデザインを制作しなければいけません。
視覚に訴えるデザインを制作するためには、まず基礎的なデザインをしっかりと勉強して、能力を身に着けておく必要があります。
デザイン関係のツールを使いこなせる人
グラフィックデザインを制作するには、デザイン関係のツールやソフトが必要不可欠です。
IllustratorやPhotoshopなど、デザインに使うソフトはさまざまですが、パソコンを使ってこれらのソフトを使いこなしていく必要があります。基本的な使い方は公式サイトやハウツー本などでも習得できますが、細かいコツや詳しい使い方はデザインの専門学校や現役のグラフィックデザイナーの元で学ぶのが一般的です。
同時に、要望やイメージをざっくりと形にする手書きラフから、IllustratorやPhotoshopを使ってデザインとして表現するまで、通してできる能力も求められます。
相手の望むデザインを制作できる人
グラフィックデザインには個性や新鮮さが必要とされますが、自分の意見だけではなく相手の意見を尊重する必要があります。相手の要望やイメージを尊重した結果、自分のデザインが却下されてしまうことも。自分のこだわりやプライドを捨て、相手の望むデザインを制作することが求められるケースも少なくありません。
相手の望むデザインを実現するために、細かい修正やヒアリングにも根気強く取り組めるかどうかもカギを握ります。
ここでは、相手の望むデザインを制作するためにはどのような人が向いているのかを詳しく解説します。
コミュニケーション能力の高い人
コミュニケーション能力は、グラフィックデザイナーの仕事において欠かせないものです。
要望に沿ったデザインを制作するためには、「聞く力」と「聞き出す力」が重要となってきます。コミュニケーション能力の高さがあると、自分のお気に入りのデザインではなく、相手の要望に沿ったデザインの制作に役立つでしょう。相手の要望に合わないデザインを作ってしまい一からやり直し、というケースを避けるためにも大切です。
加えて、グラフィックデザインの仕事には、デザイナーだけでなくディレクターやコピーライターなどさまざまな職種の人が関わってきます。パソコンに向かって淡々とデザインをするだけでなく、デザインに関わっている人とのコミュニケーションを適切にとっていくことも求められます。
提案のできる人
グラフィックデザインを制作する際、依頼する相手も具体的なイメージが固まっていない場合があります。そのような状態からグラフィックデザインを制作していくには、コミュニケーションを取って要望を聞き出すだけでなく、それに合った適切な提案をすることが必要です。
さまざまな角度からたくさんの提案ができる人だと、デザインの選択肢が広がり、相手も気づいていなかった点をデザインに取り入れることにもつながります。
柔軟性のある人
グラフィックデザインの現場では、急な変更や修正などが発生したり、テイストの異なるデザインをいくつも提案する必要があったりすることも。相手の要望に応えていくためには、根気強さとともに柔軟性をもって取り組むことが求められます。
細部にまで目の届く人
他人から見れば大したことのないような、細部の違和感や不具合も「まあいいか」で済ませず気づくことのできる人が向いています。
また、テキストの誤字やモチーフの配置バランスなど、相手も気づかなかった細かいミスが取り返しのつかない事態へと発展した事例もあります。細部まで抜かりなく目が届くグラフィックデザイナーは重宝されるでしょう。
勉強を続けることができる人
グラフィックデザインの最新トレンドや使用ソフトは常に変化し続けています。基礎的なデザインを学んだだけで満足することなく、学び続けられる人も向いているといえるでしょう。普段から意識して、インターネットから紙媒体まであらゆるメディアにアンテナを張り、勉強を続けることでグラフィックデザインの幅も広がっていきます。
まとめ:デザインのことならアドラインプラスにおまかせ!
おもに紙媒体のデザインを手がけるグラフィックデザイナーの仕事は、コミュニケーション能力や視覚に訴えかけるデザインを制作する力、柔軟性や提案力などが必要です。簡単な仕事ではありませんが、目指す価値は十分にあります。憧れるだけでなく、ぜひチャレンジしてみましょう!
株式会社アドラインプラスには、経験豊富なグラフィックデザイナーが所属しています。お客様の要望や課題を丁寧に聞き取り、イメージとぴったりのデザインを制作させていただきます。無料相談も行っているので、まずはお気軽にお問い合わせください。
-
販促物制作2023.05.17
「会社案内の作り方を知りたい」
「どのような手順が必要なの?注意点は?」
「会社案内に何を掲載すれば良いのかわからない…」自社企業のことを紹介するのに「会社案内」があると、とても便利です。魅力的な会社案内があると、ビジネスの機会も広がります。しかし、会社案内の作り方が分からずにいる人は意外と多いようです。
この記事では、会社案内の作り方を解説します。会社案内を作る目的や、掲載したほうがよい項目なども紹介します。魅力的な会社案内を作って、ぜひビジネスシーンで役立ててください。自社を知ってもらう、キッカケとなり興味を持ってくれる人が増えることにつながるでしょう。
会社案内とは
会社案内とは、名前のとおり会社のことを紹介するためのツール。会社によって、会社案内に掲載する内容は多岐にわたり、パンフレットや冊子の形をしたものが一般的です。その会社のことを知らない人にとっては、会社の第一印象を決定づけるツールのひとつとなります。
会社案内を作る目的
会社案内を作る目的は、会社のことを知ってもらうだけでなく、最終的には興味を持ってもらうことがゴールです。そのため、会社に興味を持ってもらえるような内容をしっかりと盛り込みましょう。
こんなときに使える!会社案内
会社案内を作っておくと、さまざまなシチュエーションで活用できます。
例えば、
・会社のブランディング・PR
・営業活動
・採用活動などの場面で相手に渡すと、より会社をアピールできるはずです。予算があれば、渡すシチュエーションに応じて数パターンの会社紹介資料を制作しておくのも良いでしょう。採用には特別に採用パンフレットを作る企業も多いです。
会社案内の作り方
ここからは、会社案内の作り方を解説します。
【情報収集】過去の会社案内・競合他社の会社案内を集めて研究
まずは、自社や競合他社の情報収集、分析が必要です。これまでに作った会社案内があれば、ぜひ参考にしましょう。作った当時と現在では異なる部分があるかもしれません。削除や変更をしたい項目があればピックアップしておきます。
あわせて、競合他社の会社案内もいくつか集めておきましょう。同じ業界の会社案内でも、内容は会社によって異なります。それぞれ比較して、デザインやコンセプトを研究しておくと役立つはずです。
【企画・立案】コンセプトを決める
会社案内における全体のコンセプトを決めましょう。コンセプトは会社案内全体をまとめるテーマのようなもの。コンセプトを決めるために、会社案内を作る目的や伝えたいことをはっきりさせることが大切です。1本の柱として、コンセプトが決まっているとデザインや内容もスムーズに決まります。
【原稿制作】掲載内容を決める
会社案内の方向性が定まったら、原稿制作に取り掛かります。
掲載する内容は、会社によって異なりますが、・会社概要
・沿革
・ご挨拶文
・企業理念
・取引実績/事例
・会社ロゴこれらは、会社案内において基本的な項目です。会社案内を作る目的にあわせて内容を決めましょう。項目が決まれば、どのような内容にするかを考える必要があります。内容はスペースにあわせてボリュームを調整してください。
また、会社案内では、文章だけでなく関連した写真を掲載して相手に印象付けることも大切です。掲載項目に合った写真もいくつかピックアップしておきましょう。適当な写真が手元にない場合は、新しく撮影するための手配も並行して行います。
【デザイン制作】デザイン・テーマカラーを決める
会社の第一印象を決める会社案内は、掲載内容だけでなくデザインも重要です。文字のフォントや写真のレイアウトなどによって、会社案内の出来上がりは変わります。相手にとって読みやすく、一瞬で覚えてもらえるようなインパクトのあるデザインを考えましょう。自分でデザインするのが難しい場合は、テンプレートを使ったりデザイン会社に依頼したりするのがおすすめです。
なお、テーマカラーをメインカラーとサブカラーを決めておくと、デザインに統一感が出ます。会社のイメージカラーがある場合は、イメージカラーを基調としたデザインを考えていくとよいでしょう。
【最終チェック】出来上がりを確認する
PDFや製本として完成させる前に、必ず出来上がりの確認を。誤字脱字や情報の誤りがないか、しっかりと確認する必要があります。デザインやレイアウトに違和感がないか、当初のコンセプトから逸脱していないかも確認しましょう。デザインの担当者だけでなく、必ず複数人で確認するようにしましょう。
【印刷】PDFや製本として公開
出来上がりを確認し、修正がなければ印刷会社に印刷を発注します。製本する必要のない簡素なデザインであれば、複合機やコンビニのマルチコピー機などを使って自分で印刷してください。会社案内のデザインをデザイン会社に依頼した場合は、印刷会社への発注までを一貫して任せられることもあります。印刷に慣れていない場合はデザイン会社や印刷会社に任せるのがおすすめです。
また、近年では印刷するだけでなくPDFファイル化して、自社ホームページなどで公開する企業も増えています。PDF化することで、会社案内を渡したことのない相手も閲覧でき、ビジネスのチャンスを広げられるかもしれません。
まとめ|会社案内作りで困ったら
会社案内が完成するまでにはいくつかの手順があります。コンセプトを明確化しておけば、必要な掲載項目やデザインを考えるのもスムーズに進むはずです。作り方を理解し、ビジネスの場面で重宝するような会社案内を作ってみてください。
会社案内は自分で作ることも可能です。しかし、納得できるデザインに仕上がらなかったり、掲載内容を考える時間がかかり、なかなか進まず、自分で作るのは難しいと感じている人も多いのではないでしょうか。
自分で会社案内を作るのが難しいと感じたら、デザイン会社に依頼するのがおすすめです。会社案内を制作した実績が豊富な会社なら、魅力がしっかりと伝わる高いクオリティのものを制作してくれます。
株式会社アドラインプラスは会社案内や名刺、オリジナル封筒などビジネスにおいて欠かせないツールの制作実績が豊富なデザイン会社です。丁寧なヒアリングによりニーズに合った会社案内を制作いたします。無料相談も行っているので、まずはお気軽にご相談ください。
-
コラム2023.04.28
「名刺を自分で印刷するメリットは?」
「名刺を自分で印刷する方法を知りたい」名刺はビジネスだけでなく、趣味や副業などあらゆるシーンで必要不可欠なものです。会社勤めであれば会社から支給されるケースが多いですが、自営業やフリーランスなど個人の名刺が欲しい場合は、自分で作成・印刷する必要が出てきます。
名刺を作る方法にはさまざまありますが、自分の好きなタイミングで必要なだけ印刷できると便利ですよね。しかし。自分で名刺を印刷できるかどうか分からない人や、方法を知りたい人も多いのではないでしょうか?
この記事では、名刺を自分で印刷できるかどうかや印刷する方法、メリットがわかります。これを機に、名刺の印刷に挑戦してみてはいかがでしょうか。
名刺は自分で印刷できる!
名刺は自分でも作成・印刷することが可能です。自分で印刷するのに必要なのは、プリンターや名刺用の用紙。自分で印刷した経験がないと大変そうだと思われるかもしれませんが、コツをつかめば簡単に印刷できますよ。
名刺を自分で印刷するために必要なことは?
ここからは、プリンターを使って自分で印刷するまでに必要なことを紹介します。必要な手順が分かれば、挑戦しやすくなるはずです。
名刺のデザインを作成
印刷の準備を始める前に、名刺のデザインを用意しておきましょう。デザイン用のソフトで一から作成する方法もありますが、デザインの専門知識が必要になることも。そのため、初心者は名刺用のフリーソフトやスマートフォンアプリを使うのがおすすめです。ソフトやアプリ内にはデザインのテンプレートが豊富に用意されています。好みのテンプレートを選んだら、名前や連絡先などの項目を入力するだけでデザインが完成します。デザインの細かい調整が必要ないのがうれしいポイントです。
自分でデザインを考えるのが難しい場合や、テンプレートにはないオリジナルのデザインが欲しい場合はデザイン会社へ依頼しましょう。時間と手間をかけずに、クオリティの高い名刺デザインが手に入ります。
印刷用紙を用意
デザインが用意できたら、印刷に必要な用紙をそろえましょう。名刺のデザインにあわせて自分のハサミでカットする方法もありますが、仕上がりが粗くなりやすいため、ミシン目で切り取り可能な名刺用の用紙が便利です。持っているプリンターに合ったサイズの用紙を選びましょう。
自分で名刺を印刷するなら、紙の素材にこだわってオリジナリティを出すのもおすすめです。スタンダードな再生紙から写真が映える光沢紙、独特な質感のクラフト紙など、名刺の素材はさまざまです。紙の素材にこだわる場合は、持っているプリンターで印刷できる素材かどうかも確認しておきましょう。
プリンターで印刷
名刺のデザインと印刷用紙がそろったら、いよいよ名刺の印刷です。試しに1枚だけ印刷してみて、仕上がりを確認してみましょう。頻繁に名刺のデザインが変わる場合、まずは必要な枚数ずつ印刷すると紙が無駄になりません。少しずつ、必要なだけ印刷できるのも自分で印刷するからこそ。
印刷したら、名刺のデザインにあわせてハサミやミシン目でカットしましょう。
自分で名刺を印刷するメリットとデメリットは?
自分で名刺を印刷するのは、便利な反面デメリットも存在します。ここからは、自分で名刺を印刷するメリットとデメリットについて紹介します。
自分で名刺を印刷するメリット
自分で名刺を印刷するメリットは、やはり印刷会社に依頼する場合に比べ価格が安いことです。人件費がかからずその分費用が抑えられます。
加えて、少ない枚数でも印刷しやすいのがメリットのひとつです。印刷会社の場合は発注できる最低枚数が決まっていることもありますが、自分で印刷すれば1枚からでもOK。必要な分だけ手に入ります。紙の無駄がなく、費用削減にもつながるでしょう。
自分で名刺を印刷するデメリット
一方で、自分で名刺を印刷することにはデメリットもあります。
家庭用のプリンターは、自分で用紙をセッティングする手差しトレイが一般的です。うまく用紙がセッティングできていないと、名刺デザインがズレてしまうケースも考えられます。用紙にミシン目がない場合に、ハサミでカットしても同じようにデザインがズレてしまいやすくなります。自分で印刷して作成する場合には、デザインのズレがないよう細心の注意を払いましょう。
必要な枚数だけ印刷できて便利な一方で、大量に印刷する場合には印刷会社に依頼したほうが手間にならず、費用も抑えられることがあります。コストパフォーマンスの面からどちらが良いか、よく検討しましょう。
自分で印刷するのが難しい場合は?
名刺を自分で印刷するのはデメリット・メリットの両方がありますが、中には自分で印刷するのが難しいと感じている人もいるのではないでしょうか。
プリンターが手元になかったり、自分で印刷するのが難しいと感じたりしたら、印刷会社に依頼しましょう。最近ではインターネットで申し込みをし、データを送信すれば簡単なやり取りで印刷を依頼できるサービスが増えてきています。ミスなく名刺を印刷したいときにもおすすめです。
さらに、名刺の作成に時間や手間をかけたくないなら、デザイン会社に依頼しましょう。デザインの段階から印刷の手配まで一貫して依頼できます。
まとめ|デザイン会社に印刷まで一貫して依頼!
ビジネスや趣味、副業などあらゆるシーンで活躍する名刺。プリンターや用紙があれば自分で印刷できます。自分で印刷するのは便利な一方で、印刷したときにデザインがズレやすいというデメリットも。失敗したくない場合は印刷会社に依頼するのがマストです。もし手元に名刺デザインがなければ、デザインから印刷までデザイン会社に依頼すると安心です。
株式会社アドラインプラスでは、名刺作成を承っております。あなたのイメージを丁寧に聞き取り、デザインの作成から印刷の手配まで一貫して担当いたします。無料相談も行っているので、まずはお気軽にお問い合わせください。
-
販促物制作2023.03.01
「オリジナル封筒を作るメリットは?」
「オリジナル封筒の作り方を知りたい」オリジナル封筒は、会社の名刺代わりにもなるほど重要なもの。ロゴや住所の位置、封筒のカラーなどデザインの自由度が高く、他にはない印象的な封筒を作ることができます。
近年は、個人で仕事をスタートさせる人や副業をする人も増えてきたために、ビジネスに必要不可欠なオリジナル封筒を作りたいと考える方も多いのではないでしょうか?
この記事では、オリジナル封筒の作り方や注意点、使うメリットがわかります。これを機に、手にした瞬間その会社を思い浮かべるような、オリジナリティ溢れる封筒を作ってみてはいかがでしょうか。
オリジナル封筒とは?
オリジナル封筒とは、会社のロゴや住所などがすでに印刷されたオリジナルの封筒のこと。
市販の封筒よりもデザインの自由度が高く、会社としての個性を出しやすい封筒です。ロゴの位置や封筒のカラーをはじめ、宛名の窓やフタまでオリジナリティを持たせることができます。封筒を見るだけで、その会社からの郵便物だと相手に伝えることができ、とても便利であらゆるビジネスシーンに重宝するアイテムのひとつです。
オリジナル封筒の作り方
ここからは、オリジナル封筒の作り方を手順ごとに紹介します。作り方を把握しておけば、初心者でもチャレンジしやすいはずです。
封筒のサイズを選ぶ
まずは、用途にあわせてオリジナル封筒のサイズを選びましょう。チラシや書類の発送、紙ベースでのやり取りが多ければ複数のサイズで作っておくと便利です。
一般的にビジネスで使う機会が多いのは角形2号・長形3号・長形4号となっています。
A4サイズの書類を折らずに入れたい場合は、角形2号封筒がおすすめです。大きさは240×332mm、定形外郵便物(規格内)のサイズです。書類を折って定形郵便で郵送するなら、長形3号や長形4号の封筒がおすすめ。長形3号はA4サイズ、長形4号はB5サイズの書類を三つ折りで入れることができます。
封筒のカラーを決める
一般的な市販の封筒は、茶色や白色のものがほとんど。オリジナル封筒はカラーの種類が豊富で、市販の封筒ではなかなか見かけないカラーも選べます。郵便物を手にした瞬間から会社をアピールできるよう、イメージカラーの封筒を選ぶのも良いでしょう。
封筒のデザインを考える
オリジナリティを出し、他社との差別化をはかるにはデザイン決めが大切です。ロゴの配置や会社情報のフォントなどを決めましょう。デザインのポイントとして、会社のキャッチコピーやイラストなどをさりげなく配置するのもアリ。宛名書きをする手間を省くために、窓付きのオリジナル封筒を採用している会社も多いですよ。
なかなかデザインが決まらなければ、既存のテンプレートを流用したり、デザイン会社に相談したりするのがおすすめです。
印刷・組み立て
イメージどおりのデザインができれば、いよいよ封筒を印刷して組み立てます。印刷して組み立てるには、主に3つの方法があります。
・プリンターやコンビニのマルチコピー機で印刷して自分で組み立てる
・印刷会社に印刷と組み立てを発注する
・デザイン会社にデザインから印刷と組み立てまで依頼する自分で印刷・組み立てを行うとズレやすいため、機械でスピーディーに組み立ててもらえる印刷会社に発注するのがおすすめです。
また、デザイン会社へ依頼すれば、封筒のデザインから印刷会社への手配まで一貫して任せられるケースもあります。自分での印刷や印刷会社への発注が難しい場合は、デザインの時点からデザイン会社に依頼しておくと安心です。
オリジナル封筒を作るメリット
オリジナル封筒はビジネスの場面で重宝しメリットも、豊富です。
他社と差別化できる
オリジナル封筒はブランディングにうってつけのアイテムです。会社ロゴを印刷しておくだけでも、他社にはないオリジナル封筒が完成します。ロゴの配置や封筒のカラー選びなど、他社と差別化できるポイントが豊富です。
業務の効率化につながる
オリジナル封筒は業務の効率化にもぴったりです。封筒に会社名や住所、電話番号などの情報をあらかじめ印刷しておけば、その都度封筒に手書きする手間を省けます。フタ部分に両面テープを配置すれば、糊付けも必要ありません。普段から封筒を使う機会が多ければ、オリジナル封筒の作成を機に業務の効率化につながるようなデザインを考えましょう。
デザインの自由度が高い
オリジナル封筒は、市販の封筒よりもデザインの自由度が高いのが魅力です。アイデア次第で、市販の封筒では見かけないようなニーズに合ったオリジナル封筒が完成します。中身が濡れないよう撥水・防水加工を施したり、開封前から中身がわかるよう透明な素材を選んだりして、封筒の素材からこだわるのもおすすめです。
まとめ|オリジナル封筒作りで困ったら
ロゴやイメージカラーを盛り込んだオリジナル封筒は、会社にとって名刺代わりとして一躍するケースや、ひとつの封筒によって新たなビジネスの機会を生み出すこともあります。だからこそ、他社にはないデザインを考えてみてはいかがでしょうか。デザインの自由度を活かして、ぜひ世界で1つしかないオリジナル封筒を作ってくださいね。
「デザインを考えたり、印刷会社に発注したりする時間がない」「デザインがうまくいかない」とお困りであれば、デザイン会社に依頼するのがおすすめです。初心者には難しい細かなデザインの調整だけでなく、他社にはないオリジナリティを持つ封筒作りを安心して任せられます。
株式会社アドラインプラスはチラシや名刺、オリジナル封筒など販促物のデザイン実績が豊富です。丁寧なヒアリングをもとに、ニーズにあったデザインを提案します。無料相談も行っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
-
デザイン制作2023.02.15
「デザインを依頼するときの流れを知りたい」
「できるだけスムーズに進めたい」
「依頼時には何に注意すればいいのだろう?」デザインの制作を検討していると、依頼から納品までの流れがわからず不安になることもあるのではないでしょうか?デザインについての必要な対応を把握できていないと、依頼でさえ難しく感じることもあるでしょう。
この記事では、デザインを依頼する方法から納品までの流れを解説します。注意点やデザイナーに伝える必須事項も解説します。イメージ通りのデザインを制作してもらうには、事前の準備が大切です。良いデザインに出会えるよう、依頼から納品までの流れを把握しておきましょう。
デザインを依頼する方法と納品までの流れ
デザインを依頼するまでの流れと、依頼から納品までの流れを分けて解説します。
デザインを依頼する方法
デザインを依頼する方法は、以下の手順が一般的です。
1.依頼先を探す
2.問い合わせ窓口より連絡する
3.連絡を取り合い見積もりをもらう
4.双方が納得すれば契約書を締結するまずは、デザインの制作を発注する依頼先を探します。主な依頼先には個人デザイナーとデザイン会社があり、ポートフォリオや制作実績を見て、あなたがイメージするデザインに近い人を選ぶことがポイントです。
依頼先が決定すると、問い合わせ窓口から連絡を取ります。Webサイトの問い合わせページやSNSのDMなど、依頼先が設定している窓口から依頼を検討していると伝えましょう。要件を伝えると、ほとんどの場合は見積もり書が作成されます。金額や作業の内容にお互いが納得したら正式に契約書を取り交わすこととなるでしょう。
依頼から納品までの流れ
正式に依頼が決定すると、基本的には以下の流れで納品まで進んでいきます。
1.デザイナーと打ち合わせ
2.デザインの制作を開始
3.完成したデザインを確認
4.必要があれば修正を依頼
5.再度デザインを確認
6.デザインが完成したら納品日程を調整し、デザイナーと打ち合わせを行います。依頼されたイメージにより近いデザインを制作するためにも、ヒアリングはとても重要な工程です。認識の違いを減らせるので、イメージとまったく違うデザインになるのを防ぐことができます。しっかりと要望を伝え、想像通りのデザインを制作してもらいましょう。
ヒアリングが終わると、デザインの制作に入ります。デザインが完成したら確認し、必要があれば修正を依頼します。修正回数はデザイナーによって異なり、無料で依頼できる回数や修正範囲などを指定している場合がほとんどです。デザインが大きく変わるような修正依頼は追加料金がかかる可能性があるので、必ず正式に依頼する前に確認しておきましょう。修正作業が終わり、デザインが完成したら納品となります。
依頼できる場所
デザインの制作を依頼できる場所は、個人デザイナーかデザイン会社が一般的です。
個人デザイナーはデザイン会社に比べて料金が安い傾向にあるため、近年は利用する人が増えてきました。しかしながら、個人デザイナーは実績や経歴が見えてこないケースが少なからずあります。一方で人気デザイナーは多忙で、なかなか依頼を受けられないなどといった可能性もあるでしょう。
デザイン会社は個人デザイナーに依頼するよりも金額が高くなる場合が多く見られる場合もありますが、一定のクオリティが期待できます。企業ならではの安心感があり、対応にも慣れているので、スムーズに物事を進められるのがメリットです。デザイナー1人だけでなく、複数の人が関わって制作してくれるので、偏りなく様々な視点を取り入れたデザインを構築できるのもデザイン会社の強みです。
質のいいデザインや丁寧なやり取りを希望するのなら、デザイン会社に依頼することをおすすめします。
デザインを依頼したときの相場
デザインを依頼したときの相場は、依頼するデザインによって異なります。仮にロゴの制作を依頼した場合だと、個人デザイナーなら10,000円〜80,000円、デザイン会社なら50,000円〜300,000円が目安です。
あくまで、目的はイメージ通りのデザインを制作してもらうことなので、値段だけで考えるのではなく質の高いデザインを制作してくれる場所に依頼しましょう。
【注意点】デザインを依頼するときのポイント
デザインを依頼するときは、注意点が4つあります。
・イメージを固めておく
・使う場所や用途を決めておく
・コミュニケーションがきちんと取れるか見ておく
・お金の話は契約前に確認しておく制作してほしいデザインのイメージは、依頼する前に必ず決めておきましょう。全体の雰囲気だけでなく、どのような想いを込めたものなのか、伝えたいメッセージはどのようなものなのかなど、細かに伝えるようにしましょう。使う場所や用途もイメージした上で、商品のパッケージ、会社のロゴマーク、チラシなど、どのような場所でどんな人が目にするものかを明確にしてください。
依頼先と円滑なコミュニケーションが取れるどうかも重要なポイントです。レスポンスの速さやこちらの質問に答えてくれるかなど、正式に依頼をする前に不審な点がないかを確認しておきましょう。こちらの意図を上手くくみ取ってくれたり、先回りして提案してくれたりすると安心感がありますね。
料金の確認も重要なポイントです。料金の中にどこまでの作業が含まれるのか、追加料金が必要になる作業はあるのかなど、トラブルを避けるためにも契約書を交わす前に確認しておきましょう。
デザイナーに必ず伝えておくべきこと
デザインを依頼するときに、必ずデザイナーに伝えておくべき項目があります。スムーズに制作してもらうためにも、事前に準備しておきましょう。
・使用する用途
・使ってほしいデータの共有
・画像サイズ
・納品形式
・デザイン案の数
・納期、予算制作してもらうデザインの使用用途は必ず伝えておきましょう。用途によって適した素材を選択し、イメージ通りのデザインを制作するためには必須です。使用したい画像データなどがお手元にある場合には、あらかじめそのことも伝えておきましょう。
画像サイズや、納品形式の提示も必要です。納品方法によって料金が変動する場合もありますので、事前に確認しておきましょう。
納期や予算も、同様に大切です。限られた予算の中で制作してほしい、納期はできるだけ早くなど、お互いに気持ちよくやり取りをするためにも、事前に確認しておきましょう。
まとめ|デザインの依頼はデザイン会社がおすすめ
デザインを依頼してから納品までには、いくつかの工程があります。制作してほしいデザインや事前に共有することを明確に決め、流れを把握しておけば難しいものではないでしょう。デザインを依頼するときの注意点に気をつけて、制作を依頼してください。
依頼から納品までをできるだけスムーズに行いたいのなら、デザイン会社がおすすめです。対応にも慣れており、安定したクオリティで質の高いデザインを制作してくれます。
株式会社アドラインプラスでは、プロのデザイナーが在籍し、用途やイメージにあわせたデザインを制作しています。無料相談も行っているので、まずはお気軽にご相談ください。
-
動画制作2023.01.30
「どのような動画ソフトがあるの?」
「動画編集ソフトの選び方を知りたい」商品紹介や広告など、ビジネスの場面で活用されている動画。動画編集ソフトは、カメラやスマートフォンで撮影した動画を編集するためには欠かせません。本格的なエフェクトやツールを搭載したプロ仕様のソフトだけでなく、プロのような知識がなくても使いやすいソフトも増えてきています。
そのため、多様な動画ソフトの中から自分に合ったものがわからず悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
この記事では、初心者向けからプロ仕様まで、おすすめの動画ソフトを紹介します。選び方もあわせて紹介するので、動画ソフト選びの参考にしてくださいね。
動画編集ソフトおすすめ5選

まずは、初心者向けからプロ仕様までおすすめの動画編集ソフトを紹介します。それぞれの特徴やメリット・デメリットもまとめました。
ビデオエディター(Windows)
動画編集ソフトを使ったことがないなら、まずは無料のソフトで使い方を把握しましょう。パソコンに標準インストールされている無料ソフトが手軽でおすすめです。新しくダウンロードする必要がないうえ、無料で動画編集ができます。
Windowsのパソコンに標準インストールされているのは「ビデオエディター」。フィルターやモーションといった、基本的な機能は備わっています。字幕やBGMの追加など、動画に少し手を加えたいときにもおすすめです。
iMovie(Mac)
Macユーザーであれば、まずは「iMovie」を使ってみましょう。Macに標準インストールされている無料ソフトです。初心者にとってうれしいのが、動画編集の経験や知識が少なくても動画が完成するマジックムービー機能。選択した動画から、自動的にベストシーンを特定して自動的に編集される機能です。表示画面もシンプルで、簡単に動画を並び替えたり削除したりできます。
iPhone 13から機能が追加されたシネマティックモードで撮影した動画にも対応。無料ソフトながら直感的に操作でき、便利な機能も豊富です。
Final Cut Pro(Mac)
より本格的な動画編集にチャレンジするなら、有料のソフトもチェックしましょう。Macユーザーなら、iMovieよりも機能の充実した「Final Cut Pro」をインストールできます。広角で撮影した360°ビデオに対応し、風景の動画編集がスムーズ。エフェクトの追加や方向・傾きの補正など細部まで編集可能です。
iMovie同様に、iPhoneのシネマティックモードで撮影された高画質の動画にも対応しています。焦点ポイントや被写界深度を調整することで、より魅力的な動画に仕上げられるでしょう。
価格は48,800円の買い切り制。有料のソフトですが、90日間のフリートライアル版もあります。お試し期間中に実際に触って購入を考えることができるのが大きな魅力ですね。
EDIUS X Pro
「EDIUS X Pro」は番組や映画制作の場面でも活躍するプロ仕様の動画編集ソフトです。各種動画ファイル形式への変換やレンダリングなどがスピーディーで、編集にかかる時間を大幅に減らすことができます。カメラだけでなくドローンやスマートフォンで撮影した動画もネイティブ編集が可能。音声のノイズ除去やボリューム調整など、ユーザーにとって痒いところへ手が届く充実ぶり。あらゆる動画編集の場面に重宝するでしょう。
通常版は65,780円の買い切り制。すでにEDIUS Pro 9以前のバージョンを購入したことがある場合は、アップグレード版をリーズナブルに購入する事も可能です。また学生や教職員向けのリーズナブルなアカデミック版もあります。
Adobe Premiere Pro
「Adobe Premiere Pro」は本格的な動画編集を可能にする機能が充実したソフトです。例えば、一度の編集で複数のSNSに動画を最適化できます。アップロードするSNSごとに用意されたプリセットがあるので、動画ファイル形式や縦横比を調整する必要がなく便利です。完成した動画はソフトから直接投稿が可能なので、書き出した後でアップロードする手間が省けます。さらに、音声のテキスト化機能を活用すれば音声の文字起こしから字幕化まで自動で完了できるので作業時間を一気に短縮できます。
単体プランは月額2,728円(年間プラン)。買い切りではなくサブスクリプション制です。PhotoshopやAfter Effectsなど、Adobeの他のソフトも利用する場合はCreative Cloudコンプリートプランの契約がお得。月額6,480円で20種類以上が利用でき、各ソフト間で連携することで動画のクオリティがより上がるでしょう。
初心者にもおすすめ!動画編集ソフトの選び方

使い勝手や機能などは動画編集ソフトによってさまざま。ここからは動画編集ソフトの選び方を紹介します。
無料か有料か
動画編集ソフトには無料・有料版があります。費用を抑えたい方や、まずは試しに使ってみたい方は無料の動画編集ソフトがおすすめ。作業の流れや使い方を把握するのにも役立ちます。初心者でも気軽に動画編集に挑戦できますよ。
ある程度動画編集に慣れていて、機能の充実したソフトが欲しいなら有料版を検討しましょう。有料版なら番組や映画の制作にも使われるような、プロ仕様のソフトが手に入るはずです。まずは無料お試し版からスタートして、慣れたら有料版に切り替えるのも良いでしょう。ソフトによっては、支払い方法に買い切り制と月額のサブスクリプション制があることも。利用しやすい方を選びましょう。
動画ファイル形式
編集した動画を共有サイトにもアップロードしたい場合は、サイトでサポートされている形式で動画を書き出せるかどうか確認を。例えばYouTubeはMOV.やMP4など数種類の形式でアップロードできますが、ニコニコ動画ではMP4形式が推奨されています。アップロードしたいサイトの投稿環境の確認を忘れずに。
機能
自分の制作したい動画に必要な機能があるか確認しましょう。例えば4K動画の制作には、4K編集に対応した動画編集ソフトが必要です。字幕の自動生成や手振れ補正など、動画編集をより便利にする機能もありますよ。高度な機能は無料ソフトに入っていない場合もあるので注意してください。
PCのスペックや作業環境も確認を
使用するパソコンのOS(オペレーティングシステム)がWindowsかMacかによっても、対応する動画編集ソフトが異なります。例えば、無料ソフトの代表格であるビデオエディターはWindows、iMovieはMac向け。自分のパソコンに対応していないソフトはダウンロードしても使用できない場合があるため、特に有料版の購入前には確認しておきたいところです。
また、古かったり空き容量の少ないパソコンで高性能ソフトを使うと、動作が遅くなったり画面がフリーズしたりすることも。スムーズに動画編集するためにも、パソコンのスペックに合ったソフトを選びましょう。
動画編集で困ったらアドラインプラスへ
このように、さまざまな種類のある動画編集ソフト。しかし実際には、思っていたより操作方法が難しい、作ってみてもイメージ通りの動画が完成しないなど、つまずいてしまうケースも多々あります。
「時間もスキルもない!」「魅力的な動画にしたい!」そのように考える方にとっては、デザイン会社に依頼するのがおすすめです。初心者には難しい細かな調整だけでなく、魅力的でハイクオリティな動画が完成します。また、動画制作にかかる一切を安心して任せることができます。
動画編集を依頼するには、確かな実績のある業者を選ぶことがなにより大切です。株式会社アドラインプラスでは、企業の動画撮影・編集を承っています。無料相談も行っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
-
デザイン制作2023.01.19
「ロゴ作成はどこに依頼すればいいの?」
「個人のデザイナーに依頼するメリットは?」
「相場や依頼方法を知りたい」ロゴは企業や商品のシンボルといえるほど重要なものです。新商品の発売やブランドのリニューアルなど、あらゆるシーンで必要になります。
ですが、大切なロゴ作成をどこに依頼すべきか悩んでいる人も多いのではないでしょうか?
この記事では、ロゴ作成を個人デザイナーに依頼したときの相場や依頼する方法がわかります。メリットやデメリットも解説し、個人デザイナーに依頼するべきかを判断できます。
ロゴは多くの人が目にする大切なものです。納得のいくデザインを作成するために、依頼先は慎重に選択しましょう。
ロゴを作成する4つの方法
ロゴを作成するには、主に4つの方法があります。
・無料アプリで自作
・ロゴ購入サイトの利用
・個人デザイナーに依頼
・デザイン会社に依頼無料アプリを使用し、自分で作成するのなら費用はかかりません。デザインの心得や自分で作成する時間がある人は挑戦してもいいでしょう。
ロゴサイトで購入する場合は、数あるデザインの中から気に入ったものを選びます。もとのデザインに社名を入れたり、色を変更したりできるケースもあり、手っ取り早くロゴを購入できる方法です。
個人デザイナーに依頼すると、直接デザイナーとやり取りをしてロゴを作成していきます。細かい修正や納期に対応してくれる可能性もあり、要望を伝えやすいでしょう。
デザイン会社に依頼する方法では、企業に所属するプロのデザイナーがロゴを作成します。企業とのやり取りは安心感があり、手厚い対応を受けられるのが特徴です。
ロゴ作成の相場は?
ロゴ作成の相場は依頼先によって異なります。個人、デザイン会社、ロゴ購入サイトに分けて解説します。
個人
個人デザイナーに依頼した場合、相場は10,000円〜80,000円ほど。実績や経験年数によって大きく変わります。
駆け出しデザイナーだと価格は安い傾向にありますが、デザインのクオリティは未知数です。クラウドソーシングサービスなどでは、5,000円で作成してくれる例もありました。
一方、ベテランデザイナーだと実績がある分価格は高くなります。100,000円以上で取引している人もいるので、価格やクオリティはその人によって変動します。
デザイン会社
デザイン会社に依頼した場合、相場は50,000円~300,000円ほど。
個人デザイナーに依頼するよりも価格は高くなりますが、手厚い対応や安定したクオリティが期待できます。デザイナーだけでなく、ディレクターやイラストレーターなど多くの人が関わって作成してくれるので、幅広いデザインを提案してくれることも。個人ではなく、企業とやり取りができる安心感もあります。
ロゴ購入サイト
ロゴ購入サイトの場合、相場は10,000円〜50,000円ほど。
色の変更やアレンジを無料で対応してくれるケースもありますが、サイトによってはロゴの手直しに追加料金がかかる場合もあります。必ず追加料金の有無を確認してから購入しましょう。
ロゴ作成を個人に依頼するメリットとデメリット
ロゴ作成を個人デザイナーに依頼するメリットとデメリットを解説します。
良い面だけでなく悪い面も理解して、個人デザイナーに依頼するべきかを判断する参考にしてください。メリット
個人デザイナーにロゴ作成を依頼するメリットは、デザイン会社に依頼する場合に比べ価格が安いことです。多くの人が制作に関わる企業とは違い、基本的にすべての作業を1人でこなすため、人件費がかからずその分費用が抑えられます。
また、デザイナー本人と話ができるため、細かい要望や修正箇所を伝えやすいのもメリットです。スケジュールの調整や納期の相談なども、個人デザイナーなら対応しやすい場合が多く見られます。
デメリット
デメリットは、腕の良いデザイナーを見つけるのが大変なことです。世の中には多くの個人デザイナーがいますが、すべての人が高いスキルをもっているとは限りません。実績があっても、いざ依頼してみると「想像しているのと違った」と感じる場合もあります。
良くも悪くも1人ですべての作業を行うため、提案されるデザインの幅はせまくなる可能性も少なくありません。クオリティはデザイナー次第なのです。
また、売れっ子デザイナーだと、スケジュールがいっぱいで依頼を受けてくれない場合もあります。せっかく依頼したいデザイナーが見つかっても、依頼を受けてもらえなければ意味がありません。高いスキルをもったデザイナーを見つけ、依頼するのは大変骨の折れる作業といえるのではないでしょうか。
個人デザイナーに依頼するときの注意点
個人デザイナーに依頼するときは、信用できる相手と取引するようにしましょう。
事前のやり取りで不安はないか、きちんと対応してくれるかを見極めてください。ポートフォリオがあれば必ず確認し、どのようなデザインを手がけてきたのかをチェックします。自分のほしいデザインと感じが似ているか、一定のスキルがあるかなどを見られる場合が多いです。
また、依頼する前にある程度ロゴのイメージを固めておきましょう。利用する場所、コンセプト、ロゴに込めたい想いなど、デザイナーにしっかり伝えるために考えをまとめておいてください。
個人デザイナーに依頼する方法
個人デザイナーに依頼するには、どのような方法があるのでしょうか。
依頼方法は大きく分けて2つあります。それぞれ順番に解説していきます。クラウドソーシングサービスを利用する
少しでも手間を減らしたいのなら、クラウドソーシングサービスを利用して依頼する方法がおすすめです。クラウドソーシングサービスでは、様々な個人デザイナーが登録されています。サイトによって違いはあるものの、デザイナーの実績やスキルによって評価が数値化されており、依頼するときの判断材料になります。
デザイナーとの間にクラウドソーシングサービスの会社が入り、万が一トラブルになったときにも対応してくれるので安心です。手数料を支払う必要があるデメリットはありますが、個人デザイナーと直接やり取りをするのが不安な人におすすめです。
個人デザイナーがよく利用しているプラットフォームには、クラウドワークス、ランサーズ、ココナラなどがあります。
SNSやホームページから直接依頼する
クラウドソーシングサービスに手数料を支払いたくない場合は、直接個人デザイナーに依頼する方法がおすすめです。
個人で活動している人は、高確率でなにかしらのSNSを利用しています。Twitterやインスタグラムなどで発信しているデザイナーを探し、直接依頼しましょう。注意するのは、発信内容もあわせてチェックすることです。攻撃的なことやネガティブなことばかり発信していないかなど、人間性を確かめておくことが大切です。
また、Webで検索して直接ホームページの問い合わせから依頼する方法もあります。実績やポートフォリオ、経歴などを細かく記載している場合が多いので、どの程度のスキルがあるのか判断できます。
クオリティやスムーズなやり取りを重視するならデザイン会社がおすすめ
個人デザイナーにはメリットもありますが、安定した高いクオリティのデザインを希望するならデザイン会社に依頼するのがおすすめです。
デザイン会社には、これまで培ってきたノウハウや多くの知見がたまっています。複数の人が関わることで様々な角度からデザインを構築でき、1つのデザインに固執することなく、広範囲にわたっての提案が可能です。クオリティの高さはもちろんですが、安定したパフォーマンスを期待できます。
また、企業とのやり取りは個人よりも安心感があります。対応にも慣れているので、やり取りやスケジュール管理もストレスなくスムーズに進められるのも魅力です。質の良いデザインやスムーズなやり取りを重視するのなら、ロゴ作成はデザイン会社に依頼しましょう。
まとめ|ロゴ作成はアドラインプラスにご相談を
ロゴは企業や商品にとって、とても重要なものです。それがどんなものかを顧客にイメージしてもらうだけでなく、想いや願いもいっしょに背負っています。世界でたった1つの大切なロゴだからこそ、納得のいくデザインを作成してくれる場所に依頼してください。
株式会社アドラインプラスでは、ロゴ作成を承っております。あなたのイメージを丁寧に聞き取り、プロのデザイナーが要望通りのロゴを作成いたします。無料相談も行っているので、まずはお気軽にお問い合わせください。
-
販促物制作2022.12.25
「名刺は自分で作れるんだろうか」
「アプリとか使うと無料で出来るのかな」ビジネスシーンにおいて欠かせないアイテムが名刺です。名刺制作の方法はさまざまですが、できれば費用をかけず簡単に制作したいという方も多いのではないでしょうか。
そこでおすすめなのが、スマートフォンの名刺作成アプリ。アプリから簡単に制作できて、家庭用プリンターやコンビニのマルチコピー機を使って簡単に印刷できます。
この記事では、アプリを使った名刺制作について紹介します。メリットやデメリット、選び方まで解説しますので、名刺制作の参考にしてくださいね。
アプリで名刺を制作するメリット
簡単に、十分なクオリティのデザインが完成する名刺作成アプリ。手間をかけず、気軽に名刺を手に入れたい方にとっては便利な存在です。まずは、アプリを使うメリットを紹介します。
テンプレートのデザインが豊富
名刺アプリは、種類によって数に差はあるもののテンプレートのデザインが豊富です。向きや色合いなど、さまざまなデザインが用意されています。テンプレートから、完成イメージに近いものを見つけることができるでしょう。
特にデザインにこだわりがなく、完成イメージが定まっていない方もお気に入りが見つかるかもしれません。
デザインの知識がなくてもOK!
一から名刺のデザインについて勉強し、制作するのはかなりの労力と時間がかかります。
アプリを使えば、知識がなくても十分なクオリティの名刺デザインが完成します。テンプレートを選ぶだけで、ベーシックで十分なクオリティの名刺デザインが手に入るのは、初心者には嬉しいポイントです。
時間がなくても名刺が完成!
名刺作成アプリではすでに決まったデザインのテンプレートを使うため、場所を問わない上に時間をかけず簡単に制作できるのも魅力です。完成イメージに近づけるための、デザイン会社とのこまめなやり取りも発生しません。隙間時間でササっと名刺を制作したい方にはぴったりです。
無料アプリも充実
名刺作成アプリには、無料で使えるものもあります。無料の名刺作成アプリを使えば、デザイン会社に外注した場合にかかるデザイン料は必要ありません。
家庭用プリンターやコンビニのマルチコピー機で印刷すれば、印刷会社へ依頼するよりも費用を抑えることができます。名刺制作になるべく費用をかけたくない方に、とてもおすすめです。
アプリで名刺を制作するデメリット
名刺作成アプリには、デメリットもあります。便利な一方で、テンプレートを使うことで生じる、課題も知っておきましょう。
細かな調整が難しい
アプリで使うテンプレートは、基本的に掲載する項目やデザインが固定されています。場合によっては、数ミリ単位の位置調整や掲載する項目の削除・追加ができないことも。たとえば、名前と住所の表示が重なってしまったり、見づらかったりという細かい部分までの調整にストレスを感じてしまうこともあるかもしれません。
オリジナルのデザインで制作するのは難しい
テンプレートを選ぶだけでデザインが決まるのは魅力的ですが、すでに同じテンプレートを使った名刺を持っている人も多いはずです。アプリで完全にオリジナルの名刺を制作するのは難しく、ベーシックで十分なクオリティが欲しい方向けといえます。
名刺作成アプリの選び方
ここからは、名刺を制作する前に知っておきたいアプリの選び方を紹介します。ぜひ、自分に合ったアプリを見つけましょう!
直感的に操作できるアプリがおすすめ!
名刺を簡単に制作するには、スマートフォンでも直感的に操作できるアプリがおすすめです。必要項目の入力やテンプレートの指定が、指先の操作だけで完結できるとストレスを感じにくいですよ。
中には、名刺のサイズ変更や縦・横の向き変更などに対応しているアプリも。直感的に操作できると、より完成イメージに近づけることができるでしょう。
完成イメージに近いテンプレートがあるか確認を
テンプレートの数が豊富なだけでなく、完成イメージに近いテンプレートが選べるかどうかも確認を忘れずに。デザインを重視するだけでなく、きちんと必要項目を掲載できるテンプレートを選びましょう。例えば、QRコードを挿入したい場合は、QRコードの挿入が可能なアプリ・テンプレートを選ぶことも大切です。
無料・お試し版のあるアプリを使ってみよう
名刺作成アプリには無料・有料のものがあります。
無料のアプリは費用をかけたくないときだけでなく、完成イメージを考えるのにも便利です。これまでにアプリで名刺を制作したことがなければ、まずは無料のアプリをダウンロードし使ってみましょう。また、無料お試し版のあるアプリもあります。お試し版を使って自分に合ったアプリかを確認し、必要に応じて有料版へ移行するのがおすすめです。
まとめ:アプリで名刺作成
このように、アプリを使えばデザインの知識がなくても簡単に制作可能です。しかし、細かな調整が難しいため、イメージ通りの名刺にならず挫折してしまうケースも。
「時間や手間をかけたくない!」「ハイクオリティの名刺を制作したい!」「周囲に魅力を感じてもらえる名刺を作りたい!」そのように考える方にとっては、デザイン会社に依頼するのがおすすめです。
デザインのプロに依頼することで、テンプレートでは表現できない個性的なデザインや細かな調整も叶えてくれるでしょう。印刷会社への発注など、手間のかかる作業も任せられます。
名刺デザイン制作を依頼するには、完成イメージをしっかりと形にしてくれる業者を選ぶことがなにより大切です。株式会社アドラインプラスでは、完成イメージを叶えたオリジナルの名刺デザインを提供します。無料相談も行っていますので、ぜひお気軽にお尋ねください。
-
デザイン制作2022.12.20
「グラフィックデザイナーとはどんな職業?」
「どうやったらなれるの?」
「働き方や年収を知りたい」グラフィックデザイナーとは、主に紙媒体のデザインを制作する職業のことをいいます。私たちの身の回りにある広告など、さまざまなデザインを手がけています。しかし、実際にグラフィックデザイナーの人たちはどのようなお仕事をしているのでしょうか?
この記事では、グラフィックデザイナーの働き方や仕事に就くためのポイントを紹介します。仕事内容や年収も解説し、グラフィックデザイナーになる方法や必要なスキルも紹介します。
この記事を読むと、より現場に近いイメージがつかめ自分の向き不向きを知ることもできます。ぜひ読み進めてください。
グラフィックデザイナーとは?
グラフィックデザイナーとは、広告、新聞、雑誌、本、商品のパッケージ、会社のロゴなど、日常生活でよく目にするものをデザインする職業です。紙媒体以外にも、ポスターや看板のデザインをすることもあります。
お客様の目的や意向を読み取り、第三者に必要な情報が視覚から伝わるようにデザインを考え、提案する仕事です。よく似た職業に「Webデザイナー」がありますが、Webデザイナーは紙媒体ではなく主にWebサイト(ホームページ)のデザインを行います。
媒体や制作物のサイズなどに違いがあるものの、お客様の要望を叶えるためにデザインを構築する点は同じです。
グラフィックデザイナーの仕事内容
グラフィックデザイナーの仕事の進め方と内容について紹介します。
一般的には、以下のような手順で仕事を進めることが多いです。①依頼を受ける
出版社や広告代理店などからデザインの依頼を受けます。
②打ち合わせ、聞き取り
打ち合わせを行い、お客様の目的や商品のコンセプト、狙いたいターゲット層などを丁寧に聞き取り、デザインの方向性を決定します。
③制作開始、修正
まずは、おおまかなデザインをお客様と共有します。ご納得いただけた時点から制作を開始し、デザインに必要な素材(写真、イラスト、文章など)を集め、デザインを制作していきます。
完成したデザインをお客様に提出しチェックを受け、ブラッシュアップを繰り返しながら修正します。修正作業は何度か繰り返される場合もあります。
④納品
最終チェックが終わりお客様からOKがでると、入稿データを納品して終了です。
グラフィックデザイナーの働き方
業務形態や給与・年収はどのようなものになるのでしょうか。
グラフィックデザイナーの働き方を紹介します。業務形態
業務形態には、正社員、派遣社員、パート、フリーランスとさまざまな選択肢があります。企業に就職する、スキルを活かして時短で働く、フリーランスで在宅メインの仕事をするなど、自分のライフスタイルによって環境を選べるのがメリットです。
給与・年収
求人ボックス給料ナビのデータでは、平均年収は約426万円です。(2022年11月28日現在)
月給だと約35万円、初任給は21万円程度が相場とされています。派遣社員は平均時給が約1,700円、パートだと約1,095円です。
令和3年度の日本の平均年収は約443万円なので、平均より少し低い数字が見て取れます。就労の形態や場所によって大きく異なるために、上手くキャリアを積めば平均以上の年収を得られる職業です。
グラフィックデザイナーになる方法
グラフィックデザイナーになるには、特別な資格は必要ありません。しかし、デザインの基礎やソフトの使用方法など基本的なスキルがなければ、仕事を得ることは難しいです。
現段階では基礎を学ぶために、ほとんどの人が美術系の大学や短大、専門学校へ進学します。大手の企業は基礎をしっかり学んだ人材を採用することが多いのも理由の1つです。
社会人になってからグラフィックデザイナーを目指すのなら、専門のスクールに通う、独学、未経験OKの企業に転職するなどの方法があります。
専門のスクールにはオンラインで勉強できるものもります。自分のペースで勉強できるのがメリットでもあり、短期間で効率よくスキルを習得したい人におすすめです。
独学で勉強する場合は、費用を抑えることができる一方で、モチベーションを保ちにくい、勉強できる範囲が限られるなどのデメリットもあります。
また、未経験OKの企業に転職するのも1つの方法です。求人は少ないものの、給料をもらいながらスキルを磨くことができ、学校では学べない現場の仕事に触れることができます。
グラフィックデザイナーに必要なスキル
グラフィックデザイナーには、さまざまなスキルが必要です。
デザイン能力
第一に必要なのは、デザイン能力です。視覚だけで情報が伝わるような構図、文字の大きさやフォント、写真やイラストの配置、適切な色づかいなど、デザインの基礎をどれだけ理解しているかが重要になります。
デザインソフト
デザインを制作するにはデザインソフトの使用が必須です。「グラフィックデザイナーの商売道具」といっても過言ではないので、操作スキルは不可欠です。
傾聴力
お客様の希望にそったデザインを制作するためには、要望や意向を上手く聞き取る必要があります。コミュニケーション能力でも「聞く力」と「聞きだす力」が重要になるでしょう。
取得すると有利な資格5つ
取得すると有利な資格を5つ紹介します。
どの資格も取得しておいて損はないので、ぜひチャレンジしてみてください。Illustrator(R)クリエイター能力認定試験
Illustrator(R)クリエイター能力認定試験とは、グラフィックツール「Illustrator」の活用能力を測定し、コンテンツ制作のスキルを認定する試験です。
広告代理店や出版社などの就職に有利になるほか、フリーランスや副業でも活用できる資格です。
Photoshop(R)クリエイター能力認定試験
Photoshop(R)クリエイター能力認定試験とは、画像編集ツール「Photoshop」を使用し、操作スキルや問題解決スキルを測定する試験です。
現場で多く使用されているツールで、ITやWeb制作会社などの就職に有利です。
紙媒体だけでなくWebでの仕事にも活かせます。DTPエキスパート認証試験
DTPエキスパート認証試験とは、パソコンを使用して出版物などをデザイン、印刷する技術や知識を認定する資格です。
印刷物が実際にできるまでの工程を学べるために、より現場に近い知識が身につき印刷業界への就職や転職に有利になります。
アドビ認定プロフェッショナル
アドビ認定プロフェッショナルとは、数あるAdobe製品に対する知識を習得していることを認定する試験です。
IllustratorやPhotoshopなど現場で必要になるソフトの基礎をまとめて勉強できます。まずはソフトの扱いに慣れたい、基礎的な知識を学びたい人におすすめです。
色彩検定
色彩検定とは、色の基礎や配色技法(組み合わせ方)など色に関する知識を認定する試験です。現場で役に立つ知識なので、スキルアップを目指したい人におすすめです。
グラフィックデザイナーに向いている人の特徴
グラフィックデザイナーに向いている人は、自分の作りたいものではなくお客様が望んでいるデザインを制作できる人です。しっかりとお客様の声に耳をかたむけ、課題を解決したり希望通りのデザインを制作したりできる能力が必要です。
お客様の要望を聞く力、聞きだす力、そして意図をくみ取る力がある人に向いています。コミュニケーション能力が高く、プロとしてお客様目線に立てる人にぴったりの職業です。
まとめ:デザインのことならアドラインプラスにおまかせ!
グラフィックデザイナーとは、文字や写真、図形などを上手く組み合わせ、印刷物をデザインする職業です。簡単になれるものではありませんが、働き方やキャリアアップなどで年収が上がる可能性があるので、目指す価値は十分にあります。ぜひチャレンジしてみましょう!
株式会社アドラインプラスには、経験豊富なグラフィックデザイナーが所属しています。お客様の要望や課題を丁寧に聞き取り、イメージとぴったりのデザインを制作させていただきます。無料相談も行っているので、まずはお気軽にお問い合わせください。
-
ホームページ制作2022.10.28

最新情報をリアルタイムで発信できるホームページ。
多くの人に情報を周知でき、新しいビジネスの立ち上げに欠かせないツールです。
自分で制作することも可能なため「手始めに、自分でホームページを制作してみたい」と考えている人も多いのではないでしょうか。この記事では、自分でホームページ制作をする方法やおすすめの作成サービスを紹介します。
自分でホームページ制作をする4つの方法

自分でホームページ制作をする際は、知識がどの程度あるかによって方法が少し異なります。
【上級者向け】HTML・CSSを記述して一から作成
ホームページ制作に必要なものを把握できている上級者なら、HTML・CSSを記述して1から制作してみてはいかがでしょうか。
ホームページ作成サービスでは自由に作り込めない部分も、思いのままにカスタマイズが可能です。
ただし、HTML・CSSをしっかり理解していないと記述ミスにつながる可能性が。
レイアウトが崩れたり、うまく動作しなかったりして不具合のもとになります。
原因の特定に時間と労力がかかる場合もあります。HTML・CSSの知識をつけてから制作に臨みましょう。【中級者向け】インストール型ホームページソフトの活用
インストール型のホームページソフトは、ある程度完成イメージがはっきりしており、シンプルな操作で簡単にホームページを制作したい人におすすめです。
パソコンにソフトをインストールし、文字や写真を組み合わせていけばホームページが完成します。
HTML・CSSの知識は必要ありません。【初心者向け】サーバー一体型ホームページ作成サービスの活用
サーバー一体型ホームページ作成サービスの活用は初心者にもおすすめの方法です。
ドメインやサーバーなど、初心者がつまずきやすいものはあらかじめセットアップされています。
気に入ったテンプレートを選ぶだけでホームページが完成し、時間と労力がかかりません。
サポート体制のしっかりとしたソフトを選べば、初心者でも安心です。【初心者向け】立ち上げのみプロに任せる
何から手を付ければよいかわからない場合は、立ち上げのみプロのホームページ制作会社に任せるのもひとつの方法です。
自分で立ち上げるよりもスムーズに、ニーズに合ったホームページが完成します。
なお、集客のためには、立ち上げ後もコンテンツの更新を自分でこまめに行っていく必要があります。1から自分でホームページ制作をするには?

上級者向けですが、1からHTML・CSSを記述してホームページを制作するために必要なものを紹介します。
HTML・CSSの知識
1から自分でホームページを制作するためには、HTML・CSSの知識が必要不可欠です。
HTMLとは、ホームページ上で見出しや画像、リンクなどを配置するために必要なプログラミング言語。
CSSはホームページ上のレイアウトを整えるために必要なプログラミング言語のことです。
これらの言語を完全にマスターすることで、自由度の高いホームページ制作が叶います。サーバー
サーバーは、いわゆるホームページのデータの保管場所。
サーバーにデータをどんどん蓄積していくことで、ホームページが充実していきます。ドメイン
ドメインとは、いわゆるインターネット上での住所のこと。
例えば、URL末尾の「○○.net」にあたる部分です。
なお、ビジネスや店舗などのホームページには独自ドメインがおすすめです。
好きなドメイン名を決められ、他のドメインと区別しやすくユーザーにも覚えられやすいのがメリットです。サーバー・ドメイン取得費用
サーバーのレンタルや独自ドメインの取得には費用がかかります。
費用はレンタルサーバーやドメインの種類によってことなります。
予算に合ったレンタルサーバーやドメインを選びましょう。
さらに取得だけでなく、更新・維持にも費用がかかります。取得の際には更新費用も確認を。知識がなくてもOK!レンタルプランや無料ホームページ作成サービス

ホームページ制作の知識がない場合には、レンタルプランや無料ホームページ作成サービスの活用もおすすめです。
ここからは、初心者にも使いやすいレンタルプランや無料ホームページ作成サービスを紹介します。WordPress
「WordPress」はホームページが作成できるコンテンツ管理システムのこと。
レンタルサーバー上にインストールをすると使えるようになります。無料・有料のテーマ(テンプレート)が豊富で、HTML・CSSの知識がなくても好みのデザインを選ぶことが可能です。
プラグインという仕組みを使って、SNSのシェアボタン表示やSEO対策など、さまざまな機能を追加できます。
もちろん、テンプレートで手の届かない部分はHTMLを自分で記述してカスタマイズも可能。
初心者から上級者まで多くの人に使われているサービスです。ペライチ
「ペライチ」はプロがデザインしたテンプレートに掲載したい文章や画像を入力し、公開するだけで簡単にホームページが完成するサービスです。
予約システムやオンライン決済など集客に必要な機能も充実しています。
飲食店や雑貨店など、個人店でおもに活用されているサービスです。1ページのみの公開なら利用料は無料。手始めにホームページを制作してみたい人にもおすすめです。
なお、独自ドメインの設定や便利な機能の追加には有料プランの契約が必要です。Wix
「Wix」は無料でホームページが制作できるツールです。
好みのテンプレートを選び、ドラッグ&ドロップで文字や写真を好きな場所に配置。
直感的に操作でき、初心者でも完成イメージに近いホームページに仕上がります。また、最先端のAIを使った自動作成ツールも装備。
いくつか質問に答えるだけで、AIが最適なコンテンツを自動生成しホームページが完成します。
有料版に登録すると、独自ドメインや広告非表示設定などが可能です。jimdo(ジンドゥー)
「jimdo」は初心者向けの無料ホームページ作成ツールです。
好みのデザインを選び、文字や画像を配置していくだけで見やすいホームページに。
編集画面がシンプルで、初心者でも更新が続けやすいのが特徴です。サーバー容量無制限や広告非表示など、便利な機能の揃う有料プランもあります。
まずは無料プランでスタートして、ニーズにあわせて有料プランへの移行も可能です。自分でホームページ制作をする場合の注意点

自分でホームページ制作をする場合、まとまった時間をとっておくのはマストです。
なぜなら、ホームページ制作経験がある人でさえかなりの時間がかかります。
また、サーバー・メインの取得やプロに依頼する際の費用も見積もっておきましょう。まとめ:自分でホームページ制作をするのが難しいと感じたら

今回は、ホームページを自分でつくるためのノウハウについて解説しました。
初心者だと、自分でホームページを制作するのは至難の業です。
ニーズにあったホームページが仕上がるまでかなりの時間がかかるでしょう。自分でホームページ制作をするのが難しいと感じたら、
プロであるホームページ制作会社に依頼するのがおすすめです。ホームページ制作を依頼するには、しっかりとヒアリングをしてくれる業者を選ぶことがなにより大切です。
株式会社アドラインプラスでは、丁寧なヒアリングをもとに、お客様の持つ完成イメージを形にします。
無料相談も行っていますので、ぜひお気軽にお尋ねください。>>>相談は画面右下のチャット、または、こちらの「お問い合わせ」から!