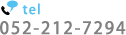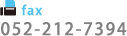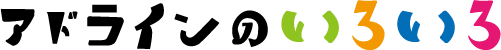
-
十五夜会2019.11.20デザイン関係者の交流会 第72回十五夜会【ご報告】

アドラインプラスの小野です。
第72回「十五夜会」にご参加いただきまして、ありがとうございました。
今回の十五夜会は、名古屋市新栄にある「ぶくパル」さんで開催致しました。
第72回「十五夜会」参加者
・作家 1名
・デザイン制作 8名
・イラスト制作 3名
・カメラマン 0名
・ホームページ制作 2名
・映像制作 1名
・その他 11名計26名のうち初参加の方は4名で、保育士をしている方、デザイナー兼DJをしている方、会社でデザイングループのマネージャーをしている方、デザイン会社を経営している方でした。
交流内容

今回のメインゲストは、豆本作家のhokori(松下 寛子)さんです。
松下さんは、ウェブ会社でプログラマー兼コーダーのお仕事をしながら、豆本作家としても活動しています。
当日は、豆本の魅力を伝えたいという事で、様々な豆本を見せて頂きながらお話をしていただきました。豆本について
はじめに豆本(ミニュチュアブック)の規定のお話がありました。
豆本は規定サイズがあって、手のひらにおさまる76×76ミリ以下のものを豆本というそうです。
また、これより大きいものをマクロミニチュアブック、小さいもので7ミリ以下の物をマイクロブックというそうです。
豆本は、歴史的にもかなり古い時からあるらしく、最古の豆本は、古代メソポタミア文明で発見された、楔文字で刻まれた約4センチのねんど板と言われているそうです。日本では、奈良時代に百万塔陀羅尼(ひゃくまんとうだらに)という高さ約6センチの豆巻物があったそうで、それは日本最古の印刷物でもあるという事でした。また、印刷技術が上がってきて、小さいものでも刷れるようになってきて日本では、江戸時代頃から豆本が増えて来たそうです。増えた理由は、携帯性があるからという事ですが、聖書などを宣教師が持っていくためとか、兵士さんが戦争に行くときにお守りとして持っていったというお話もあるそうです。
豆本を作り始めたきっかけ
松下さんが豆本を作り始めたのは、豆本作家の田中淑恵さんの本と出逢い。その本に豆本の作り方が載っていて、作ってみた事がきっかけになったそうです。豆本は、豆本作家の皆さまが作品展やクラフトフェアなどで販売されているという事ですが、ガチャガチャの景品などでもあるそうで、絵本のように絵が描かれている物から、切り絵のような物を続けた豆本もあるそうです。
当日もいろいろな豆本を見せて頂きました。
豆本の作り方を学ぶには
豆本を作ってみたい方は、松下さんが開催されているような教室へ行くのが一番手っ取り早く学べるそうですが、本なども結構出ているという事ですのでそれをみながら作るという事もできるという事でした。さらにもっと知りたい方には、日本豆本協会という協会もあるそうです。
当日は、たくさんの豆本を持って来て頂き、見せていただきました。
多彩な仕掛けがある豆本もあり、豆本の世界の深さを感じる会となりました。
次回の十五夜会
次回のメインゲストは、おたまじゃくしという屋号でイラストレーターとして活躍されている、なるさわいつおさんにお話をして頂きます。
なるさわさんは印刷会社からイラストレーターの事務所勤務を経て、フリーのイラストレータとして活動しています。また、作家活動などもされいて、色々なグループ展などにも参加されています。当日は、イラストレータで作成するイラストの描き方を説明していただけるという事です。
ご興味ある方はぜひ、ご参加頂きまして、繋がって頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。